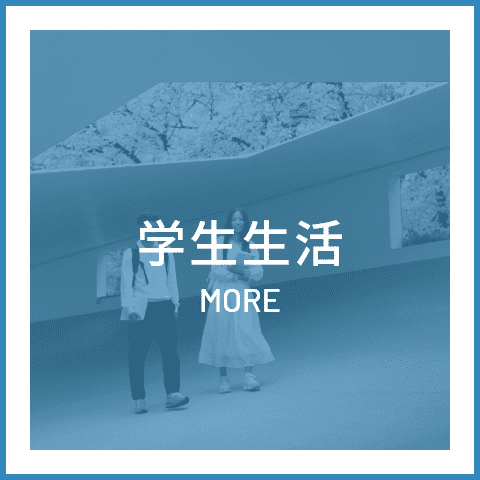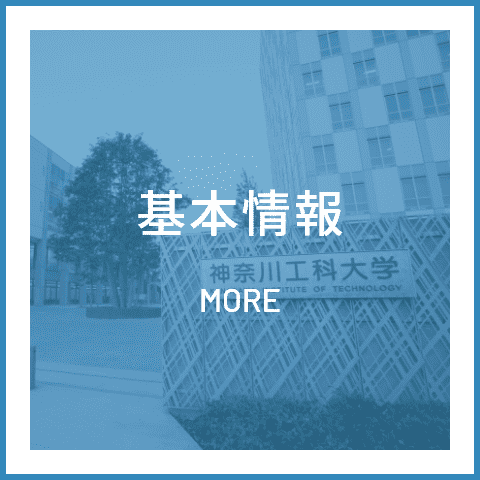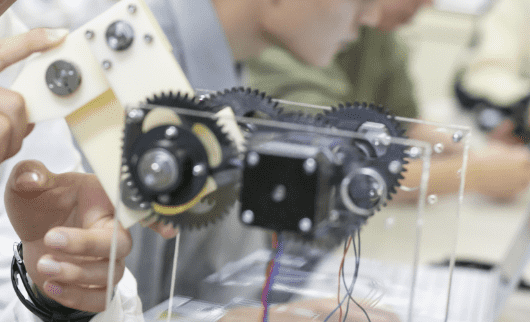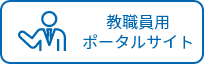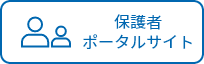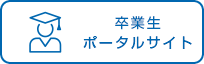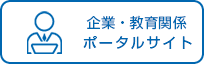【Interop Tokyo 2025 開催レポート②】トップエンジニアの現場で輝く!神奈川工科大学の学生が挑む最先端テクノロジー【学生インタビュー掲載】
2025年6月11日(水)から13日(金)にかけて、幕張メッセで「Interop Tokyo 2025」が開催されました。今年で32回目の開催となる本イベントは、最新のインターネットテクノロジーが集結する展示会であり、2025年度は3日間で13万人超が訪れました。今回は展示や会場運営を支えた本学の学生の活躍についてご紹介します。

図1 準備日のブースの様子
関連記事:Interop Tokyo 2025に向けて超広帯域ネットワーク研究センターがキックオフミーティングを行いました | 最新研究情報 | 神奈川工科大学
学生主体の多彩な展示と8K伝送実験
神奈川工科大学からは、超広帯域ネットワーク研究センター/情報ネットワーク・コミュニケーション学科が出展し、イベントの数週間前から多くの学生たちが準備を進めました。学生主体で取り組んだブース内消費電力のリアルタイム見える化システムや、「SRv6を用いた8K映像処理ワークフローの可視化」、「ブース内ネットワークの構築」 など、複数の展示が学生たちの努力によって作り上げられました。また、神奈川工科大学(神奈川県厚木市)と幕張メッセを中継で結んだ8K映像伝送実験も行われました。

図2 『SRv6を用いた8K映像処理ワークフローの可視化』(ディスプレイ表示)、および『ブース内ネットワークの構築』(機器ラック)

図3 ブース内消費電力のリアルタイム見える化システム

図4 神奈川工科大学内のローカル5Gでの8K映像伝送実験の様子。
ローカル5Gで伝送した8K映像は、神奈川工科大学がある厚木市から幕張メッセまで伝送された
Interop Tokyoの運営に携わる ShowNet Team Member(STM)への選出
Interop Tokyoの中でも特に注目されるのが、会場内のネットワーク環境をゼロから構築する「ShowNet」というプロジェクトです。ShowNetは、約2,000もの出展社提供製品やサービスと約700名ものトップエンジニアたちが幕張メッセに集結して構築される実稼働ネットワークであり、各企業の異なる規格のネットワーク機器を相互接続し、問題なく通信できるかを実証する大規模な実験場のような役割を担っています。このプロジェクトを支えるボランティアShowNet Team Member(STM)プログラムに、今年度、本学から佐々木 淳哉さん(情報ネットワーク・コミュニケーション学科2年)が面接を経て選ばれました。佐々木さんは会期前の出展社ブースのネットワーク接続チェックや、会期中のトラブル対応を担当しました。今回は、現役大学生でありながらこのSTMプログラムに参加した佐々木さんに、その貴重な経験と、ITへの情熱の原点について詳しくお話を伺いました。
現役大学生が語る、最先端ネットワークの祭典「Interop」STMプログラム挑戦記
■Interop Tokyo参加のきっかけ
インタビュアー(以下、I): まずは、この度はSTMへのご参加、誠におめでとうございます。どういうきっかけでInteropというイベントを知り、STMプログラムに応募されたのでしょうか?
佐々木さん(以下、S): ありがとうございます。Interopというイベント自体は、この大学に入ってから知りました。高校時代に名前を聞いた程度はあったのですが、大学の先輩が参加していると知って興味を持ちました。丸山研究室に入りたくてこの大学を選び、1年生の頃から研究室に顔を出していました。1年生の時に手伝いや一般入場として見学し、最新技術が集まる様子に驚きました。まさか自分もそこに携われるとは思っていませんでしたね。
I: それから、STMプログラムに応募されたのですね。
S: はい、実は先生からのアナウンスを見て、大学1年生の12月頃に軽い気持ちで応募したんです。応募フォームが公開されたので「応募ぐらいしてみようかな」と。応募することを先生に相談もしていませんでした。そしたら受かってしまって、自分でも驚きました。応募資格には技術的な部分は書かれていなかったんです。もちろん基礎的な技術は必要ですが、それ以上に協調性や、みんなと一緒にやっていけるかという意欲、やる気を見ているんだと思います。1週間または2週間、同じ人とずっと過ごすことになるので、チームで協力できるかが重要だと感じました。

図5 会場内に貼り出されたSTMの名簿と佐々木さん
I: 面接は緊張しましたか?
S: はい、すごく緊張しました。一緒に面接を受けた他の2人が社会人の方々だったので。私は当時大学1年生の十代で、社会人の方々と比べて、自分はまだまだだと感じましたね。
I: 選考で大学での取り組みが役に立ったことはありましたか?
S: 研究室のローカル5G基地局(※1)に関わるため入学後に取得した無線免許などです。去年の夏に丸山先生から「ローカル5Gやるから、無線免許取ってね」と言われたので、取った方がいいのかなと思って取得しました。受験料は大学の資格取得支援制度を利用できたので助かりました。
■参加した感想
I: 実際にInteropでの活動が始まるまで、不安はありませんでしたか?
S: めちゃくちゃ不安でした。去年の参加者リストを見ると、知っている大手情報系企業ばかりなんです。扱う内容もすべて最先端で、「ついていけるのか...?」という感じでしたね。10代は私を含めても2~3人しかおらず、最年少ではありませんでしたが、周りは院生、社会人ばかりで、まさにスペシャリスト集団でした。
I: 会期中はどのような感じでしたか?
S: 私は1週間のDeploy(デプロイ)組として参加しました。この期間は、会期前の約4日間で、出展社のブース設営やネットワーク構築が行われます。デプロイチームは、主に出展社ブースでのネットワークトラブルチェックが主な業務でした。ShowNet全体のネットワーク図(※2)をある程度理解していないと、チェック結果の判断ができないので、そういった理解は必要でした。
I: 大変だったことはありますか?
S: シフトによりますが、自分は基本的な活動が会期前の4日間、夜間シフトだったことですね。夕方から集合して深夜帯にホテルに帰り、また午後から来るというローテーションでした。丸山先生からは「いっぱい動くと思うので、体力をつけておきましょう」とだけ言われましたが、本当にその通りでした(笑)。しばらく授業を休む必要があり大変でしたが、先生方も代わりの課題を出してくれるなど温かく対応してくださいました。
I: 周りの参加者の方々の雰囲気はどうでしたか?
S: 皆さん、とても優しかったです。ネットワークが好きな人が集まっているので、分からないことを質問すると、こちらが理解するまで惜しみなく熱心に教えてくれるような方ばかりでした。
I: 学生の間に社会人と関わることで、何か得られたことはありますか?
S: ビジネスマナーの大切さを痛感しました。大学のキャリア教育で名刺交換の練習はしていたものの、実際にやってみると焦りました。会期中、名刺交換も20~30人の方と行い、次第に自信が持てるようになりました。また、社会人の方々と密に過ごす中で、今後の目標となるような理想の上司像も見つけることができました。自分の成長を感じた大きな経験です。
■ネットワークへの興味の原点
I: 佐々木さんが情報系の分野に興味を持ったのは、どのようなきっかけからだったのでしょうか?
S: Minecraft(※3)のゲームサーバーを立てたかったからです。小学校の頃に、友達と一緒に遊ぶためにサーバーを立てようと調べているうちに、プログラミングやネットワークの設定が必要だと知り、どんどん深堀りしていきました。私の周りのネットワークに携わる人たちも、最初はMinecraftから入ったという人が多いんですよ。家電量販店などに売っている家電では満足できなくなり、秋葉原で中古の業務用機材を買ってきて手探りで動かしたりオークションサイトで機材を見たり。研究室の先輩方も、みんな同じような経験を持っています。研究室では個人には手の届かない最新の機材を触れるので、本当に魅力的です。
■今後の展望とメッセージ
I: 今後はどのようなことに挑戦していきたいですか?
S: 今回はSTMとして参加したので、今後は大学の研究にもっと力を入れていきたいです。特に、今回グランプリを受賞した先輩方のメタバースでのマルチチャンネル音声の転送など、音響や音声に関する研究に興味があります。もともと音響の仕事にも興味があったので、そういった面からも研究を深めたいです。

図6 Interop Tokyo 2025 Best of Show Awardでグランプリを受賞したメタバース空間内立体音響配信システム
I: 最後に、STMプログラムへの挑戦を考えている学生さんたちにメッセージをお願いします。
S:募集要項に「技術力が必要です」とは明記されていないため、技術力よりも、意欲や「やってみたい」という気持ち、そしてめげない心を持っていれば良いと思います。 周りはプロばかりですが、「プロばかりだから行かない」ではなく、「プロに教えてもらえる環境だからこそ行った方がいい」と考えてほしいです。まずは応募してみてほしいと思います。
■インタビューを通して
Interop Tokyoに参加された皆さんにお話を伺うなかで、最先端のテクノロジーに触れ、実践的なスキルを磨き、プロのエンジニアたちと共に成長できる貴重な経験を積んだことが鮮やかに伝わってきました。Interop Tokyoというイベントが、単なる技術展示にとどまらず、実証実験を通して次世代のIT人材を育成し、未来を創造する面があることがよく分かりました。今後の活躍が楽しみです。
注記:本記事の内容はインタビュー実施時点の情報に基づいています。
関連リンク・用語解説
※1: 神奈川工科大学に100GbpsのSINET6と直結したローカル5G基地局を開設、学外エッジ装置と連携した低遅延映像処理実験が可能に - 神奈川工科大学 研究推進機構
※2: ShowNet Topology 1994-2025|ShowNet NOC Team 公開されているShowNetのトポロジー図。600名以上のエンジニアが、2000以上のノードからなるShowNetを直感的に把握し、意思疎通して構築・デバッグするためのツール
※3: Minecraft:プレイヤーが自分の思うままに世界を探索したり、建築したり、冒険したりできるゲーム