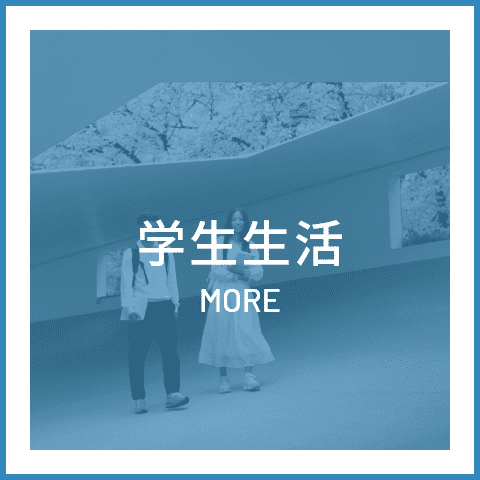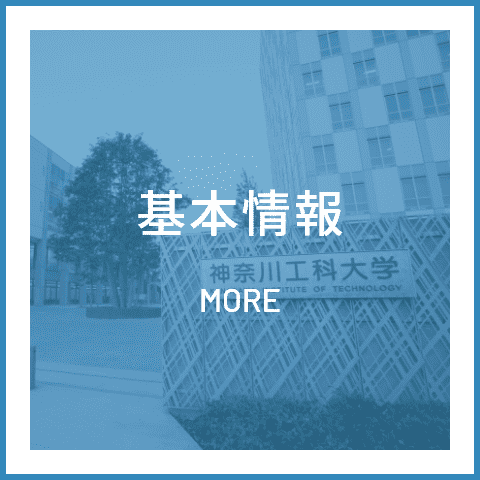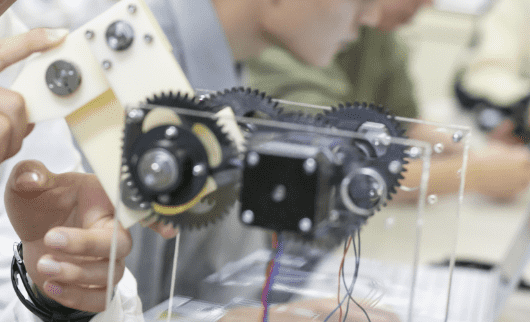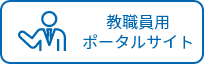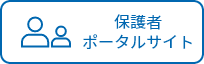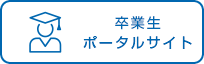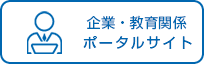環境・SDGsへの取り組み
SDGsに貢献する神奈川工科大学

神奈川工科大学は、SDGs(持続可能な開発目標)の趣旨に賛同し、教育・研究を通して、その到達目標に向けて、主体的に取り組んでいきます。
SDGsとは、2015年9月に国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された国際目標です。
SDGs活動支援拠点形成に向けた大学発環境教室プログラム
<神奈川県が主催する2019年度大学発・政策提案制度>
応用化学科(応用化学生物学科)高村岳樹教授のSDGs活動に関する提案が採択され、本学と県が協働で事業を「SDGs活動支援拠点形成に向けた大学発環境教室プログラム」として実施することになりました。
神奈川県では、専門的な知見や人材等を有する大学と一層連携強化を図ることにより、多様化・複雑化する県政の課題を解決することを目的として、「大学発・政策提案制度」を平成21年度からスタートしています。
提案する内容
地域環境団体とのワークショップの開催
各種団体(個人)の活動における、ノウハウや、解決すべき問題点など資源を共有。活動内容の紹介、今後のために大学でできることなどをまとめ、資材や道具の提供を行うとともに学内施設の貸出、イベントへのボランティア学生の配置など、今後の活動を共同提案していきます。
大学発の河川環境を知るプログラムの提供(1)
河川の水温を診てみよう!
- 各種団体と協同して、水温を図るイベントの企画や水温の現状、水温と水生生物の関連性に関したシンポジウムを実施します。
- 将来的に学習教材・プログラムになるような講座を企画します。
大学発の河川環境を知るプログラムの提供(2)
生き物調べ教室
- 神奈川工科大学と神奈川県のボランティア団体である「環境学習リーダー会」で、夏季に中津川で2回開催している生き物調べ教室がこれに相当しますが、より広域で実施する計画を各団体と協議しながら進めます。
大学発の河川環境を知るプログラムの提供(3)
マイクロプラスティックを観てみよう
- 現在、沿岸海域で問題となっているマイクロプラスティックですが、河川での汚染状況や生物への影響などを、実体験形式で実施するプログラムを提案します。河川水からマイクロプラスティックの採取、染色、観察、さらには、生物の取り込み実験などを行っています。
- 実際の河川のプラスティックごみを収集し、環境プログラムを策定します。
今後に向けた取り組み
各種団体とのSDGs活動拠点プラットフォームの形成準備
各種団体との連携を速やかにし、各団体のSDGs活動を支援、協力していく体制を早い時期に構築します。これには、ワークショップの開催やシンポジウムなどで、今後の活動についての議論を行い、拠点形成に必要な事項を共有します。
将来に向けて
- 河川から見た環境問題を学習できるプログラムを策定し、小学校などを交えた環境プログラムに展開します。
- 河川の「今」を知ることができる、「水温、プラごみ、水生生物」を測ることを中心とした事業提案を行います。
- SDGs活動拠点としての連携を深めるべく、各団体とのSDGs活動に関する連絡やプログラム開催などの案内を行い、円滑な活動への人的な補助、連絡会などを行います。
KAIT ECO活動宣言!
神奈川工科大学は、平成20年4月に「ECO活動宣言」を行い、全学生・教職員が次のマニフェスト10か条を中心に、それぞれができるECO活動を実行することと致しました。
→KAIT SDGs HUB
KAIT SDGs HUBは神奈川工科大学のSDGs活動を推進する学生組織です。学内外のSDGs関連活動に参加し、その内容や感想を発信していきます。KAIT SDGs HUBは、「KAIT 学生支援プロジェクト」から支援を受けています。
→