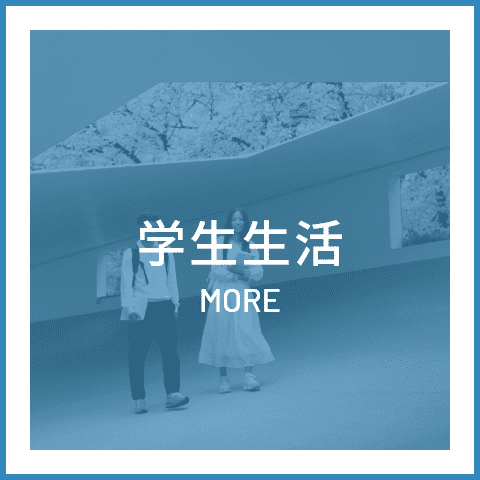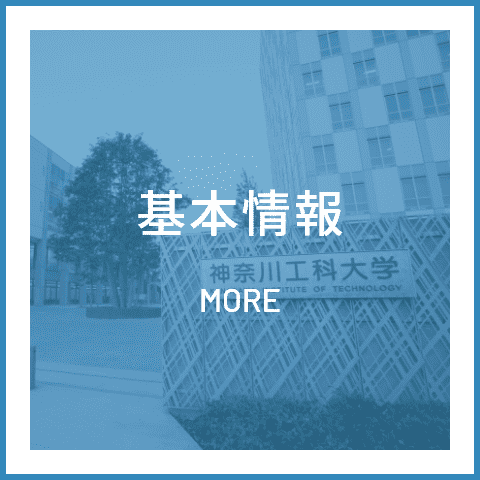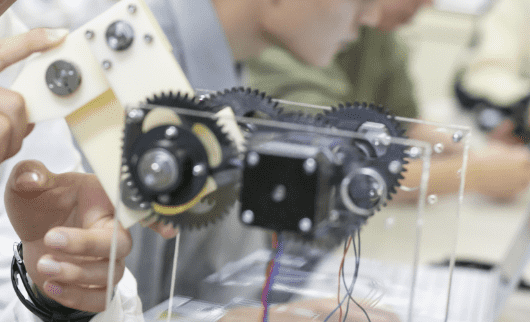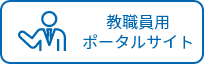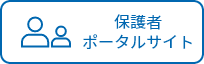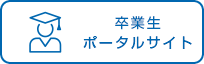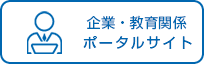【開催報告】心療内科医による特別講義&ワークショップ『痛みが視えれば世界は変わる 自分の痛みをハックせよ』
先進AI研究所では、先進的なAI技術の研究・開発に取り組み、その成果をロボット技術などへの応用にも広げています。「人の痛みがわかるロボット」の実現を視野に、AIと人との共生を目指した研究を進めています。今回は、その基盤となる「痛み」についての理解を深める特別講義の様子をご紹介します。
開催の経緯
2025年10月10日(金)、神奈川工科大学附属図書館にて、特別講義およびワークショップ『痛みが視えれば世界は変わる 自分の痛みをハックせよ』を開催しました。
本イベントは、神奈川工科大学 先進AI研究所(研究推進機構)および地域連携・貢献センターが主催し、神奈川県 福祉子どもみらい局 共生推進本部室の協力のもと実施しました。三枝 亮 准教授(情報学部 情報システム学科 人間機械共生研究室)が企画・コーディネートを担い、「ともに生きる社会かながわ憲章」(※)の理念普及に向けた活動の一環として位置づけられています。

図1 みおしん先生(写真左)と三枝准教授(写真右)
特別講義 痛みと疲労をハックせよ
講師は、心療内科医兼ペインクリニック医であり、線維筋痛症の患者としての経験や、痛みとの向き合い方について発信する活動を行っているみおしん先生です。ご自身の経験として、研修医時代に感染症をきっかけに慢性疲労症候群/筋痛性脳脊髄炎(ME/CFS)を発症し寝たきりになった経験や、子どものころから悩まされてきた疲れやすさが線維筋痛症と診断されるまで長い年月を要したことを語られました。
講義では、痛みの仕組みや、痛みは身体や神経の痛みだけでなく、不安・恐怖・怒り・疲労といった心理的要因による「心の痛み」、脳の記憶によって引き起こされる「記憶の痛み(痛覚変調性疼痛)」など、さまざまな要素が重なり合う複雑な現象であることが説明されました。
また、検査や対話では伝わりにくい痛みや疲労を可視化するための『ペインカード』(https://paincard.base.shop/)の開発経緯や、症状と折り合いをつけながら活動時間を最適化する『ペーシング』や回復体位など、みおしん先生自身が試行錯誤の末に編み出した工夫についても紹介されました。

図2 ペーシングについて説明する みおしん先生
ワークショップ:自分の痛みを可視化せよ

図3 みおしん先生が開発したペインカード
ワークショップでは、まず参加者がペアになり、「人生で一番つらかった痛みの記憶」をテーマに、自分の体験を思い出しながら、『ペインカード』を使って、その時の痛みを選び、その痛みを感じていたときの表情を再現して写真を撮影。撮った写真は『フォトシュシュ』(https://photoshushu.net/)というアプリを通じて、スクリーンに共有され、参加者同士がお互いの痛みの種類や、背景にあるエピソードを知るきっかけになりました。

図4 スマホをシュッとスワイプするだけで、リアルタイムに投影できるフォトシュシュ

図5 フォトシュシュで共有された写真。
それぞれの痛みが表情から伝わります
続くワークショップでは、これまで感じた痛みについて、心・体・記憶に向き合いながら画用紙やクレヨン、マスキングテープを使い、自由なアート制作に挑戦しました。学生たちは平面や立体でそれぞれが感じた痛みを表現していきました。

図6 あなたの痛みは何色? 直感で画材を選ぶところからスタート

図7 痛みを思い出しながら自由に表現

図8 その時感じていた痛みを表現しながら、作品と撮影

図9 フォトシュシュで共有された作品
完成した作品は、フォトシュシュで共有。制作者から、どんな痛みを表現したのかを発表していきました。作品の説明を聞くことで痛みがより具体的に伝わることで、「痛そう」と思わず声を上げたり、普段見えない「心の痛み」に共感したり、「そんな痛みを抱えていたのか」と理解することで相手を気遣う場面もありました。参加した学生たちは、十人十色な『痛み』について理解を深めました。

図10 最後はみんなで発表会
みおしん先生は、痛みは身体と心からの救難信号であり、我慢せずに自分の状態を理解しようとすることが大切だと語られました。また、痛みを抱えていても人生をあきらめる必要はなく、さまざまな人と出会い、異なる価値観に触れることで、自分らしい働き方や生き方の選択肢が広がると伝えられました。

図11 みおしん先生と受講者
関連リンク・用語解説
※「ともに生きる社会かながわ憲章」について
2016年7月26日の津久井やまゆり園事件を受け、このような事件が二度と起きないようにと同年10月14日に神奈川県と県議会が制定しました。本憲章は、「すべての人のいのちを大切にし、誰もがその人らしく暮らせる地域社会をめざす」ことを基本理念とし、当事者の視点に立った施策の推進が進められています。神奈川県では、大学・企業・自治体と連携しながら、出前講座や「ともいきアート展」「ともいきメタバース」など、共生社会の実現に向けた多様な取り組みを展開しています。なお、みおしん先生は「ともいきメタバース講習会講師」も務めています。
※随時追加予定
本件に関する問い合わせ先
研究推進機構 研究広報部門
E-mail:ken-koho@ccml.kanagawa-it.ac.jp